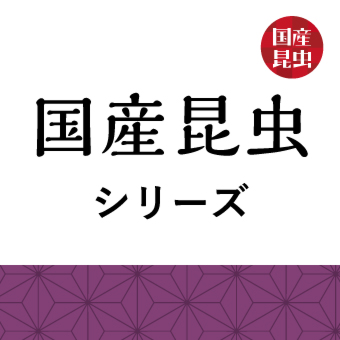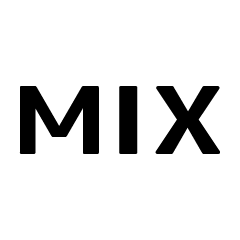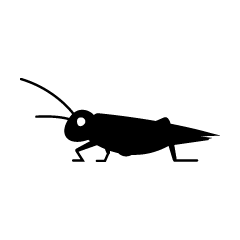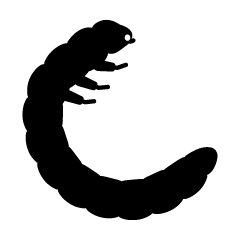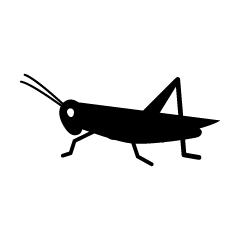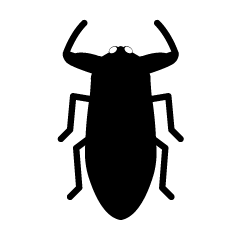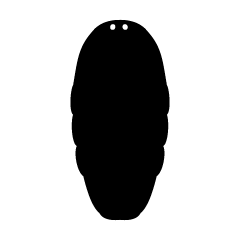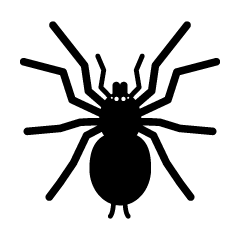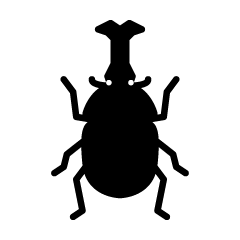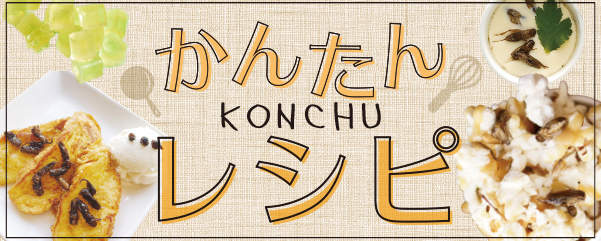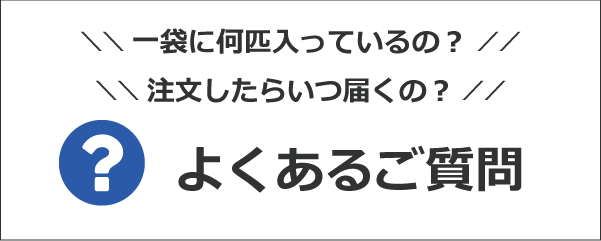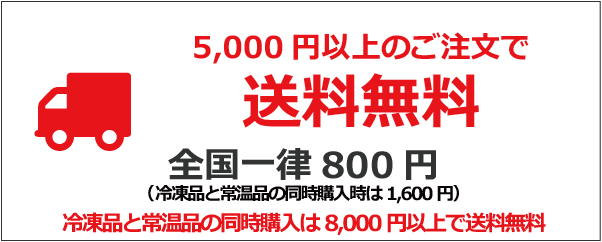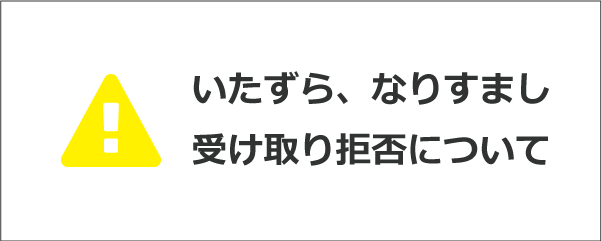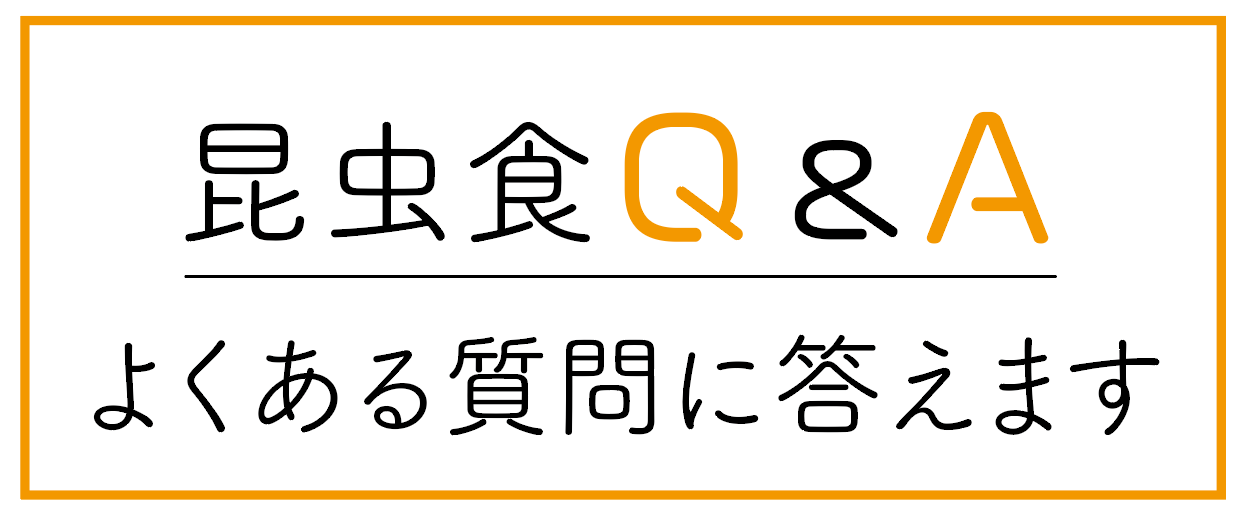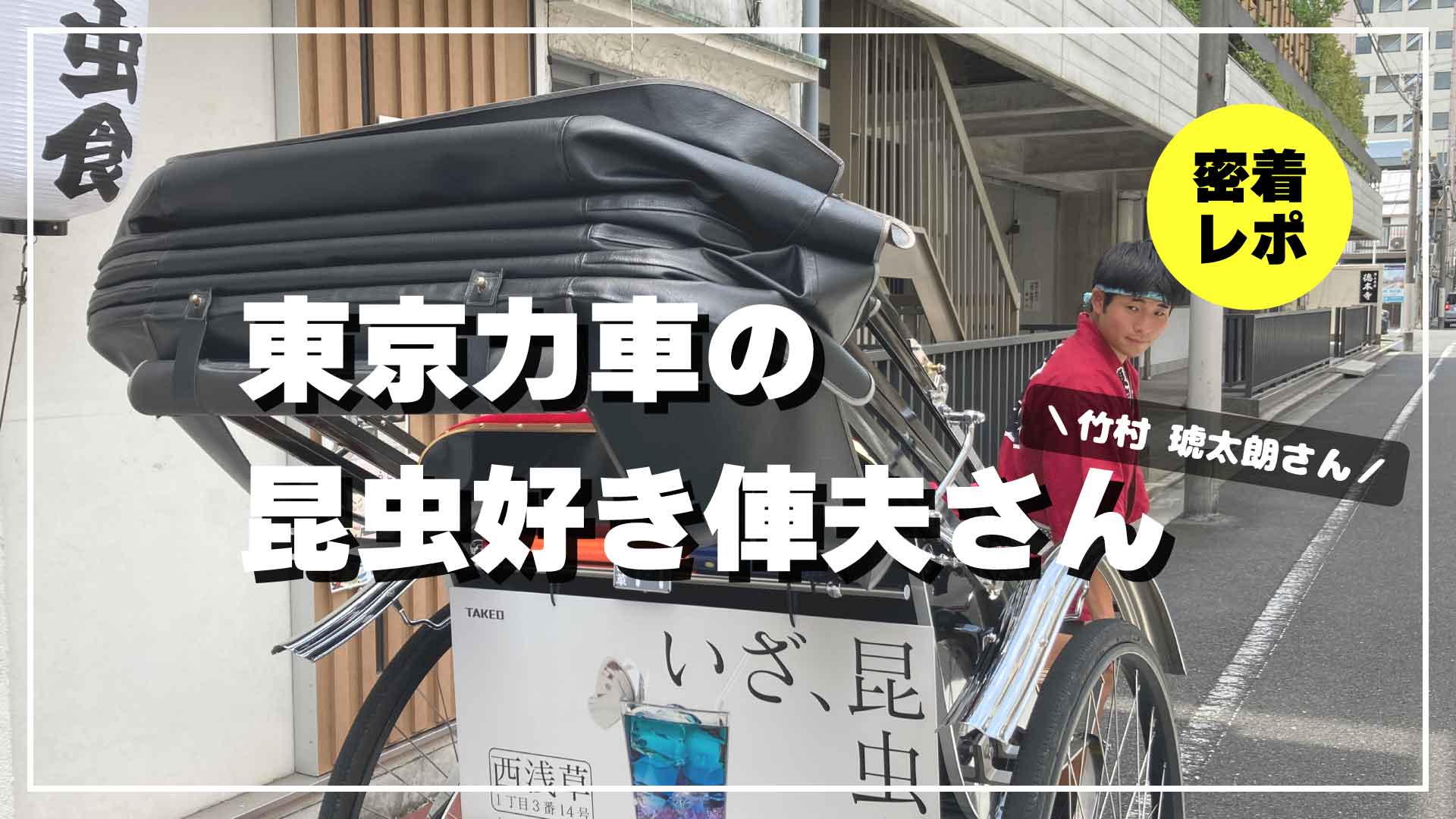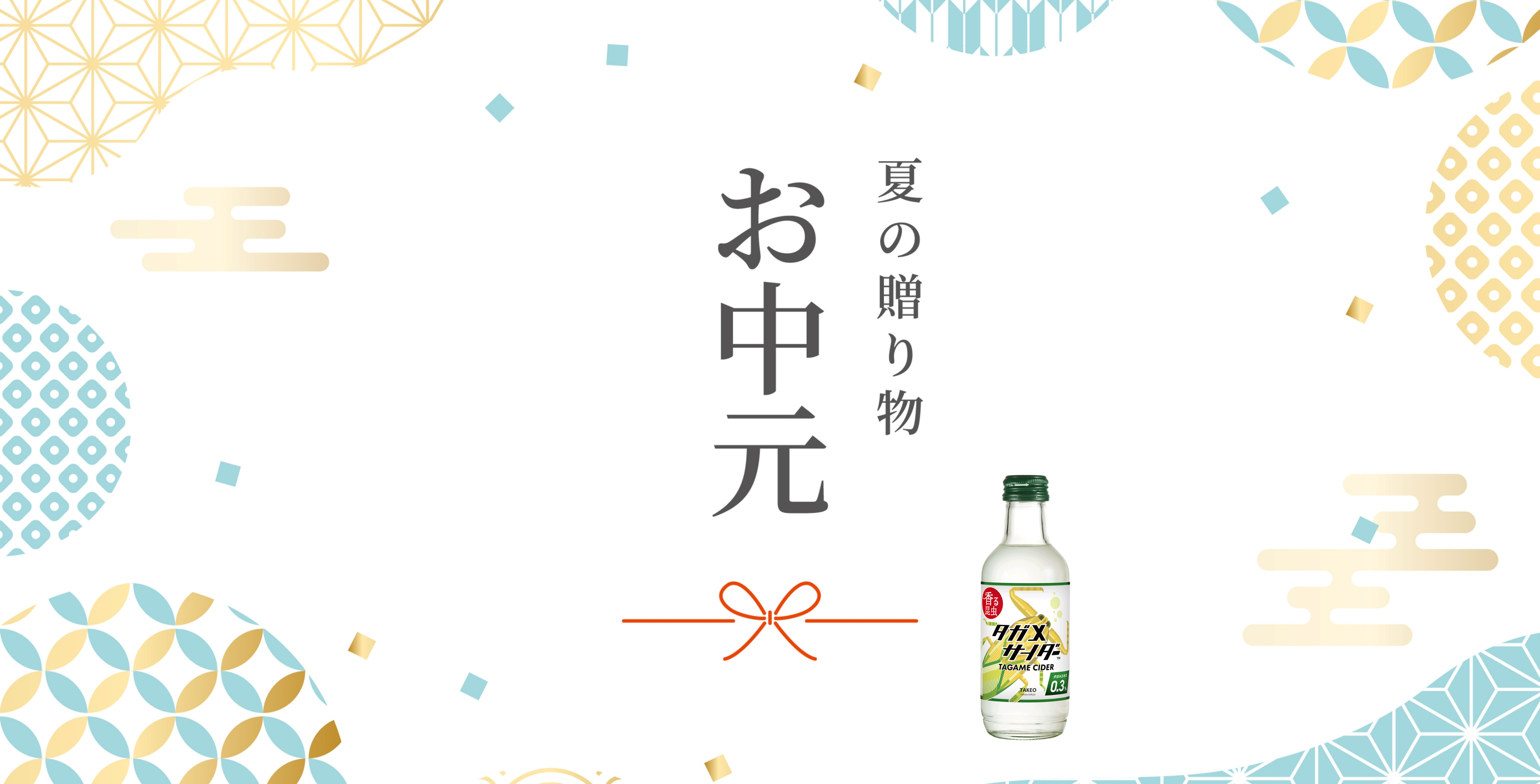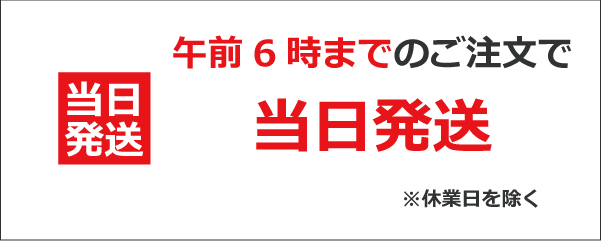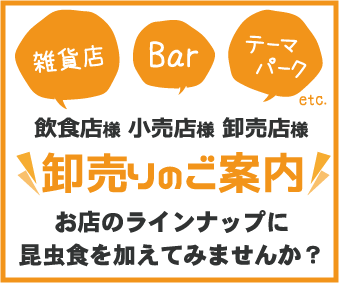前回の『蟲喰ロトワこと佐伯真二郎とは?インタビュー』に引き続き、自身が理事長を務める食用昆虫科学研究会について佐伯真二郎さんに伺いました。
食用昆虫科学研究会とは、日本初の「昆虫食を科学する研究会」で、研究を通じて昆虫食の価値を見出し、社会をより良くするための昆虫食のあり方を提案するために結成されました。研究会の発足理由やその具体的な活動内容についてお聞きします。
『昆虫食界のアベンジャーズ』お互いに助け合わないとうまくいかない
ー 食用昆虫科学研究会を始めたきっかけを教えてください。
2011年、既に昆虫食をテーマに研究をしていた学生さんは何人かいました。しかし、日本に昆虫食を総合的に様々な角度から研究できる大きな研究室がありませんでした。それに加え、教授が昆虫食について全然知らなかったり、専門知識があまりなかったんです。
それで声を掛け合ってお互いに情報交換をして研究を進めようというのが、食用昆虫科学研究会の始まりです。それぞれ所属が人文地理学であったり、農学であったり、開発学であったりと、いろんな切り口があって、そのどれもお互いに助け合わないとうまくいきません。
私は農学・理学のあたりから昆虫食の研究をしていますが、人文地理学や開発学といった文系の方たちの議論はすごく難しいんです。それぞれ切り口が違うので、どうすれば多方面から見ても良いものができるのだろうと考えました。昆虫食をトータルな文化として成立させて、いろんな面から見てもらおうと考えたんです。
まず、昆虫食のポテンシャルと昆虫食の活用のされ方を比べた時に、ポテンシャルが高いにも関わらず、現状ではあまりにも活用されていないことに驚かされました。
『どの面からみても昆虫食が活用されない理由が見つからないのです。』
理由があれば対処できますが、理由がないんです。昆虫食はむしろ活用した方がいいという理由のほうが浮き彫りになります。そうすると学術的な調査・研究だけでは社会は変わらないのだろうと考えました。
躍進!サイエンスアゴラ賞受賞(2013年)
ー 普段はどのような活動をされているのですか?
研究会自体で昆虫食イベントを開催したり、また一般向けのサイエンスイベントに毎年「昆虫食どうですか?」とアプローチする活動をするようになりました。今年も11月にサイエンスアゴラに参加します。
去年は試食会をしていたのですが、通りがかりに見て「うわっ」って離れていく人もいますが、サイエンスに対して知識欲を持っている方たちなので、嫌な顔をしつつも話をきいてくれる人もいます。
手応えとしては、2013年にサイエンスアゴラ賞というものを頂いて、参加者の投票で一番をいただけました。サイエンスというコンテツとしても、良いものができているのだと思います。
昆虫食があたりまえの食材の一つになるために
ー 研究会のビジョンに掲げられている「あたりまえな食料の一つとして、あたりまえに昆虫が利用される社会」それを実現するにはどうしたら良いと考えていますか?
現在、昆虫食を一般的な食材として消費するには、数がまだ足りません。人や動物に食べさせる研究をするには、量が必要になってきます。そうすると今のところ手に入る昆虫はコオロギくらいしかありません。
私なら専門はバッタですが、各々研究者が注目した昆虫を養殖する拠点をつくることが大事だと考えています。そして研究を進めると同時に昆虫食を売ったり、試食会のようなイベントを開催したり、余ったフンを加工して何らかの工芸品にするという、トータルとして文化的なものをつくっていくことだと考えます。

文化的アプローチ『食べなくてもいい昆虫食』
ー なるほど、トータルとして昆虫食の文化をつくることが普及の鍵なんですね。そのため、食べるための研究もされていると思いますが、文化的なものがつくられるために現在取り組んでいることはありますか?
私が昆虫食を文化的なものにしたいと考えた時、まずは昆虫そのものをモチーフにして作品を創り上げている作家さんに注目しました。そういった作家さんに話を聞いてみると、アートフェスなどで作品をみた方々に「ああ、気持ち悪い。」と声をかけられるそうです。昆虫が苦手な人と既に向き合っている作家さんだからこそ、昆虫食の作品をつくってもらいたかったんです。
実際に彼らがつくったものをみると、私が予想していた昆虫食とは異なる作品が出てきました。やはりこれは表現のプロにパスを出したほうが、フィクションを含めてどんどん昆虫食のバリエーションが広がっていくのだと実感しました。
作家さんの中には食べたことはないけれど、想像で作品をつくってみた方もいます。また昆虫食展に来られた方には、試食会に参加するほどではないけれど、昆虫食の作品を見たくて来場されたお客さんもいましたね。
昆虫食に興味を持つ方が意外と多いし、食べるに至らなくてもちょっとチラ見してみたいという方が、裾野としてもっと広いことがわかりました。
いままでの昆虫食を普及させるイベントは、「さっそく食べましょう」というものばかりでした。でも、食べないまでも気になるという方がもっといる。そういった方に「昆虫食を食べませんか?」と一足飛びではなく、「昆虫食はどうですか?」と投げかけてみる。食べない昆虫食の普及活動があると、今後面白くなっていくと思います。
研究会としての今後一年の活動
ー 研究会のこれから一年の目標を教えてください。
食用昆虫科学研究会として、今後一年は専門分野を拡げていこうと思っています。そこで別の専門家の参入を歓迎しています。今回の展示会でもそうなんですが、アーティスト・表現者の方が昆虫食をテーマにすることを支援していきます。
もう一つは一般社会に向けて、『昆虫食をどうデザインするか』を考えています。私も感じているのですが、研究者や昆虫食実践者は食べ慣れてくると、一般の人たちとの感覚がズレてくるんです。
一般の人は、昆虫の姿があると美味しくなさそうに見え、私たちは昆虫の姿形が美味しく見えるんです。そのズレを調整してくれるデザイナーの必要性を感じています。
ー 佐伯真二郎さん、この度はインタビューありがとうございました。

まとめ
今回、私が印象に残ったことは、昆虫食が普通の人にも親しみやすい存在となるために、様々な試みをされていることも勿論ですが、そのために自身の限界を認め、違う視点を持っている人に助けてもらうという、食用昆虫科学研究会理事長・佐伯真二郎さんの謙遜さでした。
また、初めての人には昆虫食を押し付けるわけでもなく、「食べなくても良い」「見るだけで良い」という懐の深さにも驚きました。人に寄り添い、益になる昆虫食の未来と可能性を感じさせてくれました。
2017年11月24日(金)~26日(日)には、東京で開催されるサイエンスアゴラ2017に食用昆虫科学研究会として参加されるそうです。食用昆虫科学研究会の活動や、昆虫食に少しでも興味をお持ちでしたら参加されてみてはいかがでしょうか。